ディープなインドネシアングルメ
日本でエスニック料理がブームになって、そろそろ20年くらいでしょうか?
まだまだ人気は衰えず、それどころか最近はスーパーやコンビニでも手軽に買える食材・食品も増えてきました。
以前は、ややマニアックなイメージもありましたが、今はごく一般的なメニューとして浸透してきています。

エスニックと一言で言っても、タイやベトナムなど、内包する国は様々です。
今回は、その中でも東南アジアの広大な島国・インドネシアの、奥深いグルメをご紹介します。
チキン大国の実力
インドネシアは、かつて欧米が香辛料を求めて遥々やって来たほどのスパイス産出国です。
今でも料理の支度は、スパイスの調合から始めます。
その為、臭みのある肉や魚の調理には強く、各地で発展してきた肉・魚料理には目を見張るものがあります。
インドネシアは、人口の9割がイスラム教徒であり、イスラム教では豚は禁忌とされているので、豚が使われることはあまりありません。
そして、牛肉はまだ庶民にとってはお高いため、実は一番人気があるのは鶏肉です。

インドネシア料理といえば、フライドチキンであるアヤム・ゴレン(ayam goreng)が有名かと思います。
しかし、他にもまだまだ、外せない鶏肉料理があるのです。
まず、甘辛な味付けなら、照り焼きチキンのアヤム・バカール(ayam bakar)や、串焼きのサテ・アヤム(sate ayam)です。
どちらも炭火焼きの香ばしさがあり、甘醤油であるケチャップ・マニスという調味料を使っているのでコクがあります。
サテ・アヤムには、ピーナッツソースがかけられているので、日本の焼き鳥とは違った味わいが楽しめます。
煮込み料理なら、ココナッツミルクと香辛料で長時間煮込んだ、オポール・アヤム(opor ayam)が絶品です。
ココナッツミルクのクリーミーさと、柔らかくなったチキンは相性抜群で、めでたい日に作られることも多く、一度は食べてみたい一品です。
また、インドネシアでは、蒸し焼き料理も実は豊富です。
あちこちにバナナの木が生えていますが、そのバナナの葉で食材を包んで蒸し焼きにします。
料理が一層香り高くなるのです。
そうした中でもオススメなのが、ペペス・アヤム(pepes ayam)と、ガランアサム(garang asem)でしょう。
ペペス・アヤムは、ハーブや香辛料と一緒に蒸したスパイシーチキンです。
風味がしっかり染み込んでいるけれどくどさはなく、ご飯によく合います。
ガランアサムも同じ蒸し焼きですが、こちらはトマトやナガバノゴレンシという、木の実が入っているため酸味があり、またココナッツミルクもあるのでコクがあります。
さっぱりとしていて、やみつきになる美味さです。
インドネシアならではの食材たち
また、日本では中々お目にかからない食材もたくさんあります。
豚は禁忌と書きましたが、その代わりでもないですがヤギ肉は比較的ポピュラーです。
独特の乳臭さは、香辛料と合わせるとまろやかな旨味に変わります。
串焼きのサテ・カンビン(sate kambing)や、スープカレー煮込みのグライ・カンビン(gulai kambing)など、どれもがっつりと食べ応えのある料理です。
また、島国なので魚介も豊富です。
タイやクエ、ロブスターといった高級食材がお手頃に食べられるのも魅力ですが、地元の人たちに愛されている味も忘れてはいけません。
あまり知られていないけれど、日本人にも人気なのが、バンデン・プレスト(bandeng presto)と呼ばれる、ターメリックなどの香辛料を塗り込んでから圧力鍋で炊いた魚です。
バンデンは日本語ではサバヒー、ミルクフィッシュなどと呼ばれます。
あっさりした味わいの白身魚ですが、小骨が多いのが難点です。
それを圧力鍋で骨まで柔らかく調理してしまうので、簡単に美味しく食べられてしまうのです。
味がしみて、ホロホロのバンデンはおつまみにもぴったりです。
他にも、海水魚以外に淡水魚も広く食べられています。
淡水魚は泥臭くて苦手…なんて人もいるのではないでしょうか?
だからこそ、インドネシアの調理法はぴったりなのです。
ハーブやスパイスでサッと味つけして揚げた、グラミーのグラメ・ゴレン(gurame goreng)やナマズのレレ・ゴレン(lele goreng)は、淡水魚が苦手な人にこそ食べて欲しい一品です。
カリカリの皮と香り高く、ホクホクの身の取り合わせがまた絶妙です。
更に、これまた外せないのがアヒル料理です。
日本でも鴨南蛮などが食べられていますが、こちらのアヒルはもっとポピュラーな存在と言えるでしょう。
鶏肉と似て非なるそのお肉は、より歯ごたえがしっかりとあり、鉄分もたっぷり含まれています。
そんなアヒル肉は、唐揚げベベック・ゴレン(bebek goreng)にしても美味しいのですが、よりディープなメニューがベベック・ゴレン・サンバル(bebek goreng sambal)です。
サンバルとは、インドネシアではレストランでも家庭でも欠かせないチリソースです。
そのチリソースと調味料で一旦アヒルを炒め、その後に揚げ、再び先ほどのサンバルと和えます。
ピリ辛の中にチリの風味が食欲をそそり、クセになること間違いなしです。
まとめ
いかがでしょうか。
インドネシアは赤道直下の年中温暖な気候から香辛料の栽培に適していて、昔からそれらを用いた調理が根付いていました。
風味を良くするだけでなく、ものが腐りやすいという環境でも上手く食材を使うことが出来ていたのです。

数多あるスパイスの複雑な組み合わせも、長い歴史の中で洗練されてきました。
インドネシアの料理にはそうした先人の知恵が存分に詰まっています。
宗教の事情から制限のある食材もありますが、一方で多民族というお国柄から、各地で多様な食文化が発展してきました。
国内にいる民族は少数民族も含め200とも300とも言われています。
このような背景から、例えばチキンという食材一つ取っても、多様な食べ方があるのです。
各地・各民族で好みの味付けが違うため、比較的安価な鶏肉には各地の様々なレパートリーが反映されることになりました。
各地の鶏肉料理を食べ比べしてみると面白いと思います。
また、日本ではあまり食べる機会のない食材も楽しんでみたいところです。
イスラム教では年に一度、神に感謝を込めて供物を捧げる犠牲祭という行事を行いますが、古くからその際に供物とされてきたのがヤギでした。
そのため、ヤギ肉調理のノウハウはお墨付きです。
一方、日本もインドネシアも共に島国でありながら、違いが顕著に表れるのが海産物ではないでしょうか。
太平洋や日本海にはいないような、南国ならではの魚を是非味わってみたいものです。
アヒルもまた、日本にいるものとは少し種類が違います。
その多くが素朴なオーガニック農法で飼育されていて、庶民的でありながらエキゾチックさを感じ取ることができます。
日本の5倍の国土を持つインドネシアの奥深いグルメの世界、皆さんも是非触れてみてください。
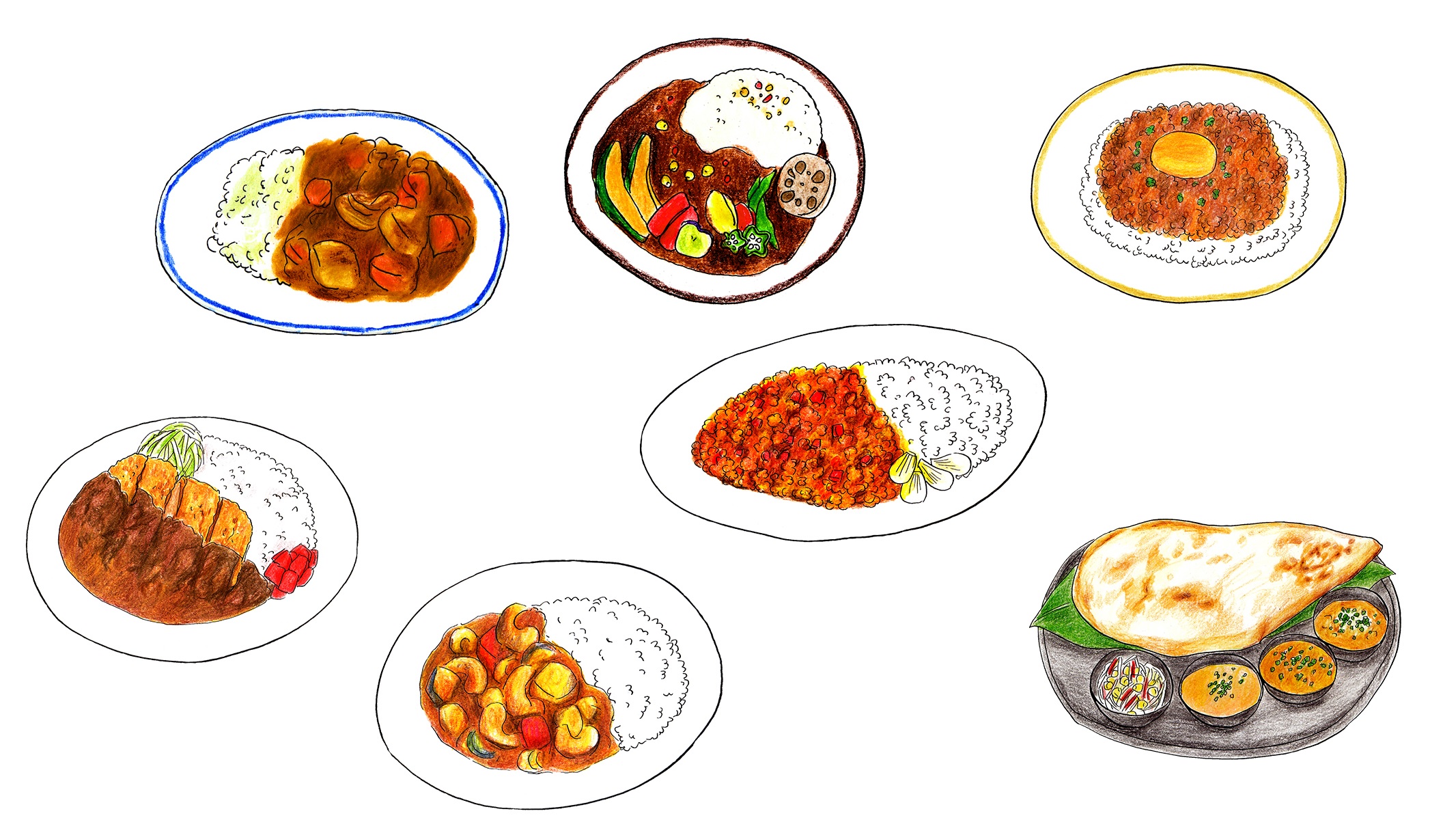
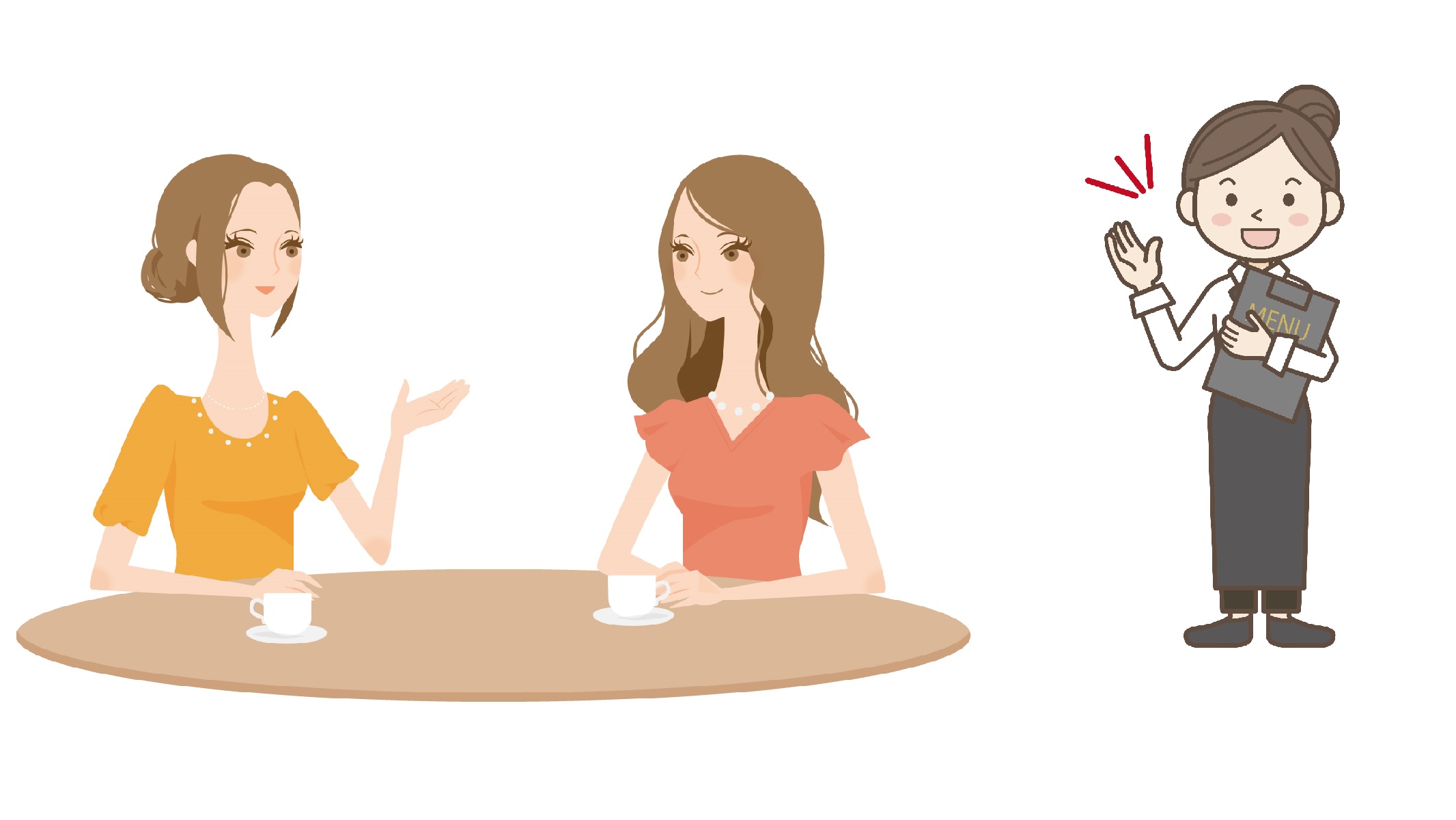

コメント