日本における大豆の自給率
大豆といえば何を思い出しますか。

大豆は、豆腐・納豆・煮豆・しょうゆ・みそ、などなど、私たち日本人の生活に欠かせない食品の原料になっています。
この大豆、どこで作られているか見たことはありますか。
平成29年9月から順次、すべての加工食品の原材料の産地が表示されることになり、原材料名を見ると、「大豆(国産)」とか「大豆(アメリカ産)」などと表示されています。
日本国内で使用するすべての大豆のうち、国産大豆が使用されている割合を「自給率」と言いますが、この自給率は平成27年度実績でたったの7%です。
日本は食料自給率が低いと言われて久しいですが、1割にも満たないのは非常に危機感を感じます。
もし異常気象などで、外国産大豆が大きな被害を被った際には、諸外国は外国へ農産物を輸出する余裕などなくなります。
またたく間に日本国内で大豆製品の流通が、マヒしてしまうことが容易に想像できます。
さらに大豆の自給率が7%という数字以外にも、大豆の使用について見ていくと様々な興味深いことがわかります。
次に大豆の用途と輸入・国産の割合についてご紹介します。
大豆の用途 〜輸入大豆と国産大豆〜
日本国内で使用するすべての大豆の使用は、多い順に「大豆油」「食品」「その他(種子用など)」に分類されます。
大豆油には全体の66%が使われますが、これはすべて輸入大豆が使われます。
食品(豆腐、納豆、煮豆、しょうゆ、みそなど)用に使われるのは28%です。
そして残り6%は種子(国産大豆の栽培用)に使われています。
このデータからわかることは、大豆は、食品として私たちの生活に馴染みあるものでしたが、その食品の倍以上の大豆が、「大豆油」に使われているということです。
大豆油はいったい何に使われているのでしょうか。
実は食用だけでなく、工業用としても使われています。
食用の場合は、サラダ油、マヨネーズやドレッシングの原料、またマーガリンやショートニングの原料にもなっています。
マーガリンやショートニングは、コンビニやスーパーで売られている大量生産のスナック菓子やパンに、必ずと言っていいほど使われています。
他方、工業用の場合は、ペイント、ワニス(木材などの表面保護に使われる・ニス)、リノリウム(天然素材から製造される床材)、印刷インキなどに使われています。
また可塑剤や樹脂の原料にもなりますし、最近ではディーゼルエンジン用の、代替バイオ燃料としても注目されています。
次に、食品用の大豆の国産大豆と輸入大豆の比率に注目したいと思います。
食品用の大豆には、国産と輸入の両方が使われており、その比率は国産24%、輸入75%です。

豆腐、納豆、煮豆、しょうゆ、みそ以外にも、大豆を使った食品というのは、油揚げ、凍り豆腐、がんもどき、湯葉、豆乳、きな粉、炒り豆などがありますが、これらの食品で国産大豆が使われている割合が2.5割なのです。
意外に国産大豆の割合が少なくありませんか。
日本で作られている大豆は、種子用を除いてすべて食用に使われているのですが、それでも2.5割とは驚きです。
日本人のソウルフードとも言えるこれらの食品が、日本で生産された大豆で作られたのではなく、アメリカ(1位)、カナダ(2位)や中国(3位)からの輸入品で作られている方が7.5割と、非常に多いのです。
おそらく輸入が盛んではなかった昔の時代においては、すべての大豆加工食品は、国産大豆で生産されていたでしょう。
国産大豆が貴重なわけ
昨今は、食品の「安心・安全」がうたわれるようになり、消費者も自身の健康に注意してできるだけ、体にいいものを食べようと言う風潮が以前に比べると浸透しています。
国産だろうが外国産であろうが、食べられればいいと言う時代ではなくなってきているようです。
そういった健康志向の方々に、知っていただきたい大豆についての情報があります。
それは輸入大豆の農薬汚染についてです。
ドキュメンタリー映画「世界が食べられなくなる日」によると、輸入大豆は、船積みされる際に保存のため、虫や獣害を防ぐために大量の農薬をかけています。
そしてその農薬のおかげで、大豆の積み込みをしている作業員が、農薬による体調不良を訴えているといいます。
輸入大豆は、非常に多くの農薬が収穫後に散布されています。
この映画では、遺伝子組み換え作物のラットへの影響として、発がん性があることを暴露していますが、農林水産省によると、日本に輸入されている大豆は、遺伝子組み換えではないので、この心配はありません。
しかし、農薬の害ももちろん発ガン性もありますし、運搬する作業員に影響が出るほど多くの農薬をかけていることは、「安心・安全」とは、かけ離れた印象が残ることは避けられません。
だからこそ、国産大豆は輸入大豆に比べて、生産、流通過程などの「素性がわかる」ものという意味で非常に貴重であると言えます。
まとめ
日本人のソウルフードとも言える、納豆・豆腐・しょうゆ・みそなどの原料の大豆について、「国産と外国産の比率(自給率)」や「大豆の用途」について紹介をしました。
特に、食用大豆の国産の割合が2.4割という、非常に低い数値であることに着目しました。

その上で、外国産大豆では、収穫後における農薬の散布があるという点で、国産大豆がいかに貴重かについて述べています。
参考:農林水産省「大豆の豆知識」に発表されている大豆にまつわる数値から

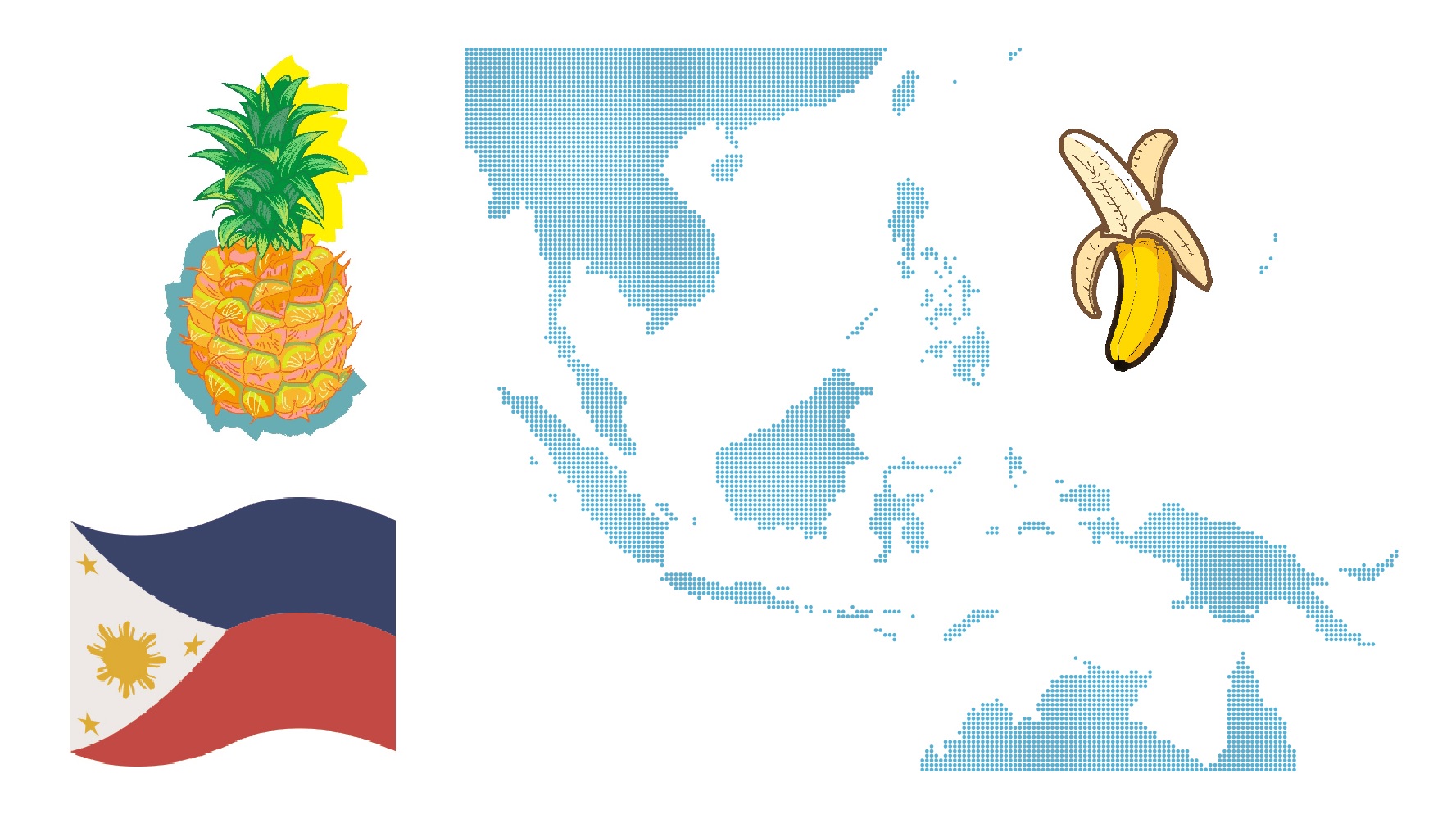
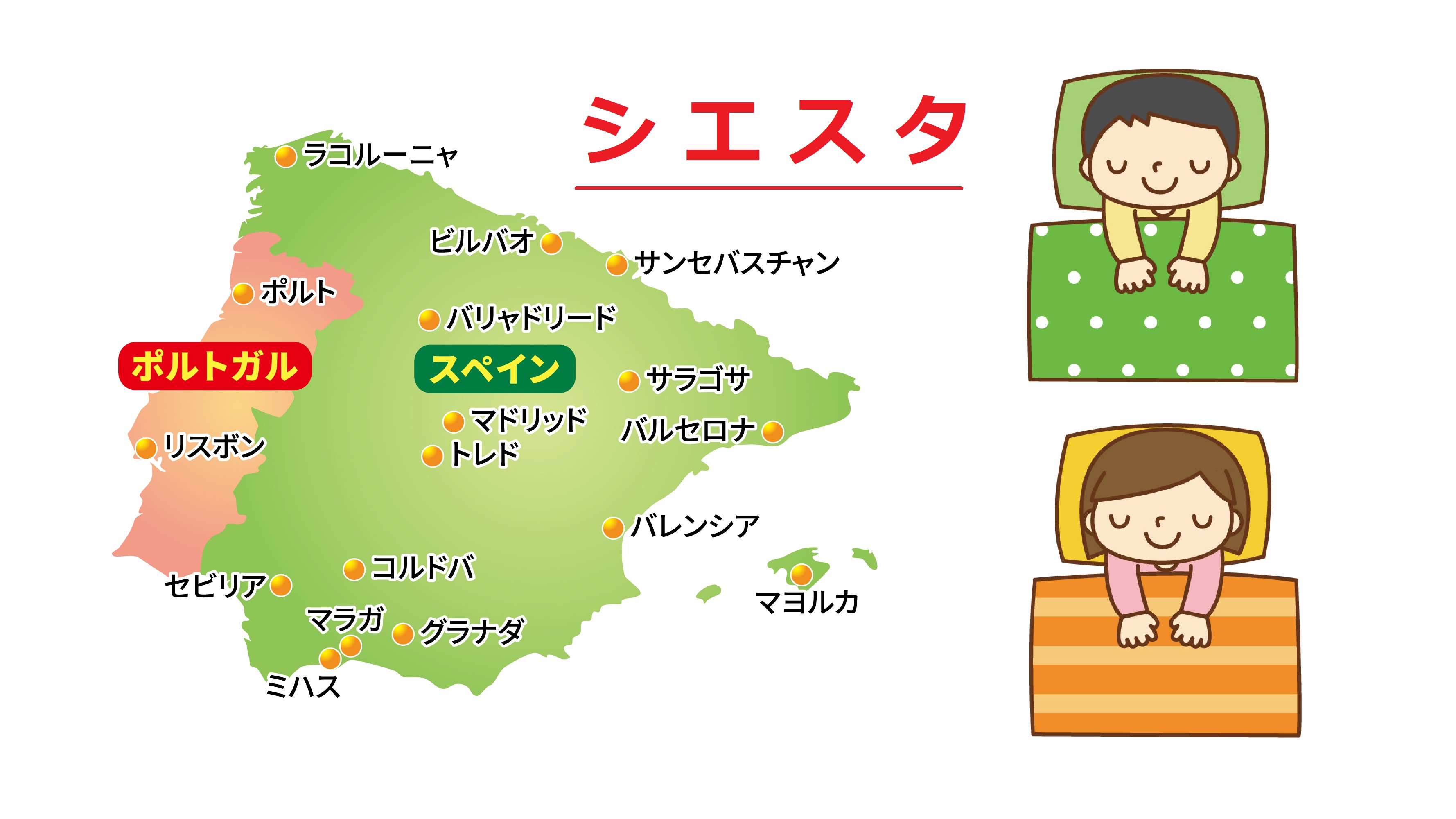
コメント